共有持分の評価額の決まり方は?売却価格の決め方についてもご紹介

不動産は丸ごと売却するだけでなく、共有持分だけを売却することもできます。
共有持分の評価額は、不動産の評価額に応じた決まり方をするため、把握しておくと売却時にスムーズです。
今回は、不動産の共有持分の決まり方や不動産の評価額の決まり方、売却価格の決め方についてご紹介します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産の共有持分における評価額の決まり方

取得した不動産の共有持分の評価額には、一定の決まり方が存在します。
共有持分の評価額は、不動産の評価額と個人の持分割合によって決まるのです。
すなわち、共有持分における評価額の決まり方を式にすると、以下のとおりになります。
共有持分の評価額=不動産全体の評価額×持分割合
したがって、共有持分の評価額を調べたいときは、不動産の評価額を調べる必要があります。
共有持分の持分割合の決まり方
不動産の共有持分における個人の持分割合は、不動産を購入したときの負担割合に応じて決まります。
たとえば、2人で購入価格の半分ずつを出し合って購入したのであれば、お互いに2分の1ずつ共有持分を所有することになるでしょう。
また、不動産の共有は相続でも発生することがあり、持分割合は相続人ごとの法定相続分に応じた決まり方をします。
共有持分も相続の対象になるため、世代を下るとどんどん分割されて割合が小さくなっていくのです。
共有者同士で持分を譲渡したり贈与したりすると、それぞれの持分割合が変動する点にも注意しましょう。
持分割合の確認方法
現在どれだけの持分割合を所有しているのかを確認するときは、登記簿を見ると良いでしょう。
不動産の登記簿謄本の権利部(甲区)には、持分と所有者の名義が記載されています。
古い不動産などでは記載されていないこともありますが、現在は売買契約時に司法書士が記載するのが一般的です。
また、毎年送られてくる固定資産税納税通知書や、名寄帳で確認することもできます。
固定資産税納税通知書は、基本的に共有者のなかの代表者1人に送られてくるため、見せてもらえるのであれば依頼しましょう。
書類を紛失したときや見せてもらうのが難しいのであれば、自治体役場で固定資産税評価証明書を取得する方法があります。
相続登記などでしっかり登記されておらず、持分割合がわからないときは遡って過去の所有者を調査し、登記登録しなければなりません。
戸籍謄本を調べて相続人や相続割合を算定して持分を計算する、契約書に書かれた持分割合を確認するなどの方法があります。
▼この記事も読まれています
不動産売却時の必要書類!提出するタイミングごとの必要書類を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産の評価額の決まり方

共有持分の評価額の決まり方には、不動産の評価額が大きく影響しています。
そのため、共有持分の評価額を計算するためには不動産の評価額も知っておかなければなりません。
不動産の評価額は、土地の価格と建物の評価から成り立ちます。
土地の価格にはさまざまな基準がある
土地の価格の評価基準は「公的な評価基準」と「過去の取引額」の2つです。
公的な評価基準には、公示地価、基準地価、相続税評価額、固定資産税評価額の4つがあります。
公示地価は、国土交通省が土地の適正価格を形成するために示している土地価格の指標です。
基準地価は、都道府県や政令指定都市が示している土地価格の指標であり、公示地価の対象にならない地域も対象になります。
相続税評価額は、相続や贈与時に課される税金の計算の基礎になる価格です。
道路の路線ごとに価格が定められている路線価方式と、固定資産税評価額に決められた倍率をかけて計算する倍率方式の2種類があります。
固定資産税評価額は、毎年課される固定資産税の計算に用いられる評価額です。
さらに、地域ごとに似た土地の過去の取引額を土地の価格の相場として評価しています。
建物の評価基準は1つ
建物の評価は土地と異なり基準が1つしかなく、基本的に固定資産税評価額によって算出されます。
固定資産税評価額は土地と同様、固定資産税を計算するための基準であり、3年に1回見直されているのが特徴です。
建物では、評価する時点でその建物を建て直すといくらの建築費がかかるのかと、経年劣化でどれだけ価値が減少するかによって評価が決められています。
なお、評価を更新するときは前年の評価額を上回らないように調整がおこなわれているため、材料費が高騰しても固定資産税評価額は上がりません。
不動産の価値を決める一般的な基準
不動産の評価額には、不動産の価値を決める一般的な基準が影響してきます。
不動産がある土地の立地条件や土地の大きさと形、近隣の状況、その不動産の需要と競合の供給状況などです。
都市部や利用頻度の高い駅の近くなど、利便性が良い位置にある不動産ほど価格が高くなります。
また、土地は広くて形が正方形や長方形に近いほど価格が高く、台形や三角形、旗竿地など歪な形をしているほど価格が低いです。
社会情勢や景気の動向も不動産の価格に影響し、これらの条件が不動産の査定額などに反映されます。
▼この記事も読まれています
不動産売却で買取保証を利用できる条件とは?メリットや注意点を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産や共有持分の売却価格の決め方
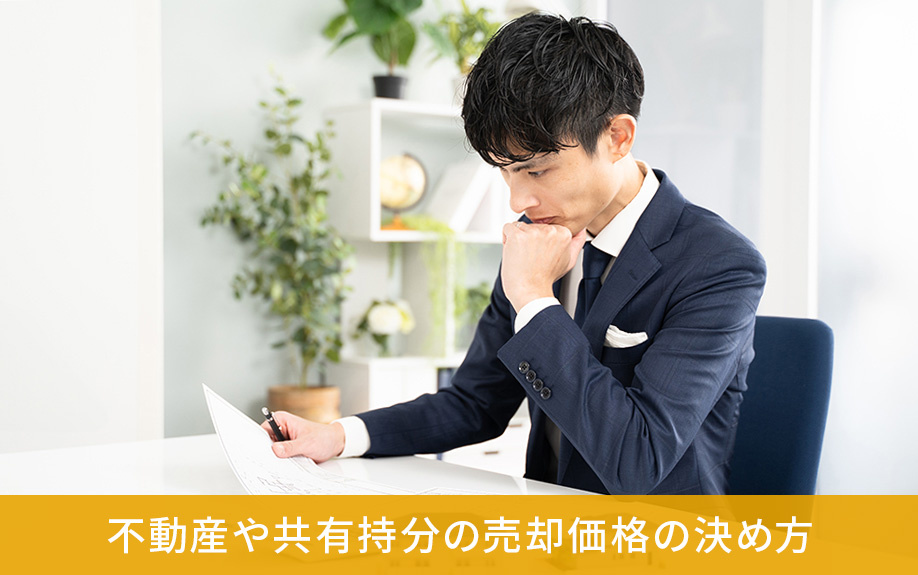
不動産を売却するときは、その不動産の売却価格を決める必要があります。
共有持分についても、売却するのであれば売却価格を決めて取引することになるでしょう。
不動産の売却価格を決めるときは、売り出し価格と成約価格の違いに気を付ける必要があります。
売り出し価格と成約価格の違い
不動産の売却価格には、売り出し価格と成約価格の2種類があります。
売り出し価格とは、買主の方が不動産の売却活動を始めるときに決める売却希望価格です。
そのため、不動産の広告などには売り出し価格が記載されますが、実際にこの価格で売れるとは限りません。
実際には価格交渉などで売り出し価格から値引きされることも珍しくなく、最終的に決まった売却価格を成約価格と呼びます。
売り出し価格は不動産の相場価格や不動産会社による査定額をもとに算出され、これらの価格が正確に算出されるほど成約価格との差が小さくなるのが特徴です。
成約価格の決め方
不動産の成約価格は、売主と買主の交渉の結果によって決まります。
売り出し価格をもとに値引き交渉などがおこなわれ、それぞれ希望する額が相互に一致したときにそれが成約価格となるのです。
実勢価格などの計算に用いられる売却価格とは、基本的にこの成約価格を指します。
不動産は似た条件のものは数多くあれど、まったく同じものは2つとありません。
そのため、基本的に売主側が「売りたい価格」と買主側の「買いたい価格」が一致したときに、その不動産ならではの価格が成立します。
共有持分の売却価格
共有持分を売却するときや、逆に買い取ってもらうときの価格も基本的には売主と買主の相談によって決められます。
基本的には、不動産の価格を持分割合で割ったものが共有持分の相場価格です。
ただし、不動産全体ではなく共有持分のみを買い取るときは、不動産全体を買い取るときよりも面積あたりの単価が低くなります。
共有持分のみを所有しているとき、所有者はその不動産を自由に処分することはできません。
そのため、共有持分を単純な持分割合に応じた価格で売り出すと、買主から値切られる可能性があります。
逆に、共有者同士で持分をやり取りするときに、どうしても売りたくない方がいると、その方から買い取る価格が高額になる可能性もあるため注意が必要です。
共有持分においても、売主と買主が双方に納得しない限りは売却が成立しません。
▼この記事も読まれています
単純売却の概要とは?メリットと利用するための注意点についても解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
共有持分の評価額は、不動産の評価額に対してどれだけの持分割合を所有しているかによって決まります。
不動産の評価額については、土地と建物でそれぞれ異なる評価基準があるのが特徴です。
共有持分を売却するときの価格は売主と買主が相談したうえで決めますが、交渉によっては相場より高くも低くもなります。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む






